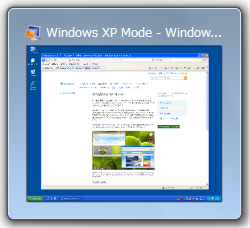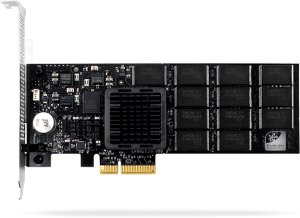Tag Archives: チューニング
Intel SSD 730 Series 高負荷ベンチマーク速度比較結果

read/writeが混在する高負荷I/Oを連続して掛けた時に各社のSSDがどのような性能特性を示すか、ベンチマークソフトで計測して各メーカーが誇るフラグシップモデルと速度比較を行います。
今回は2014年3月に日本国内で販売が開始されたIntel SSD 730 Seriesの240GBモデルが検証対象です。
730 Seriesは、インテルが「データセンター向けSSD」と位置付けるDC S3700 Series・DC S3500 Seriesのアーキテクチャをベースに開発して、コンシューマー市場向けに投入した製品です。2013年に実施したDC S3700・DC S3500のベンチマークでは、インテルDCシリーズが現行製品最速クラスの高速応答性能を発揮することを確認しました。今回は、730 SeriesがインテルDCシリーズのDNAをどこまで受け継いでいるのか、ベンチマークによって明確にします。
Intel SSD DC S3500 Series 240GB 高負荷ベンチマーク結果&チューニングTips

高いI/O負荷を連続して掛けた時に各社のSSDがどのような性能特性を示すか、ベンチマークツールを利用して計測していきます。
今回は2013年6月に日本国内で販売が開始されたIntel SSD DC S3500 Seriesの240GBモデルが検証対象です。
Intel SSD DC S3500 Seriesでは、上位モデルのDC S3700 Seriesと同じアーキテクチャが採用されています。インテル製の「PC29AS21CA0」コントローラーとMicron製のキャッシュDRAM、さらには突然の電源断時にデータ保護を行うキャパシタ(the power loss capacitor)を搭載しており、これぞまさにデータセンター向けのSSDと言える製品に仕上がっています。ちなみに、S3700とS3500の構造的な違いは、S3700がより信頼性の高い「HET-MLC NAND」を搭載している点です。
2013年5月に実施したS3700の高負荷ベンチマークでは、S3700が現行製品最速クラスの高速応答性能を発揮することを確認しました。あとはS3700の販売価格がもう少し下がれば自作PC用途での利用も広がるのになぁ…という印象だったのですが、そこに価格をS3700の約半分に抑えたS3500が投入されてきた訳です。筆者としては、S3500の高速応答性能に特に期待して今回の検証を実施しました。
Intel SSD 335 Series 240GB 高負荷ベンチマーク結果&チューニングTips

高いI/O負荷を連続して掛けた時に各社のSSDがどのような性能特性を示すか、ベンチマークツールを利用して計測していきます。
今回は2012年10月に日本国内で販売が開始されたIntel SSD 335 Seriesの240GBモデルが検証対象です。330 Seriesの後継となるインテルのメインストリーム向け主力製品であり、amazon等の通販サイトでは常に売り上げランキング上位に入る人気商品です。
Intel SSD 335 Seriesは、330 Seriesを踏襲してSandForceコントローラー「SF-2281」を搭載しており、圧縮アルゴリズムを活かした高速なスループット性能を安定して発揮することが予想されます。SandForceコントローラーを搭載する製品は「直線番長」「0fill番長」等とも揶揄されますが、read/writeが混在する高負荷I/Oが30分以上継続した時にも実力を発揮できるでしょうか。
Intel SSD 530 Series 240GB 高負荷ベンチマーク結果&チューニングTips

高いI/O負荷を連続して掛けた時に各社のSSDがどのような性能特性を示すか、ベンチマークツールを利用して計測していきます。
今回は2013年8月に日本国内で販売が開始されたIntel SSD 530 Seriesの240GBモデルが検証対象です。520 Seriesの後継となるインテルの次期主力製品であり、消費電力を520 Seriesの1/4以下に抑えた、ノートPCやUltrabook等での利用を強く意識した製品としてリリースされています。メインストリーム向けのIntel SSD 335 Seriesと並んで、amazon等の通販サイトでは常に売り上げランキング上位に入る人気商品になっています。
Intel SSD 530 Seriesは、520 Seriesを踏襲してSandForceコントローラー「SF-2281」を搭載しており、圧縮アルゴリズムを活かした高速なスループット性能を安定して発揮することが予想されます。SandForceコントローラーを搭載する製品は「直線番長」「0fill番長」等とも揶揄されますが、read/writeが混在する高負荷I/Oが30分以上継続した時にも実力を発揮できるでしょうか。
東芝SSD HG5d 256GB 高負荷ベンチマーク結果&チューニングTips

高いI/O負荷を連続して掛けた時に各社のSSDがどのような性能特性を示すか、ベンチマークツールを利用して計測していきます。
今回は東芝SSD HG5dシリーズの256GBモデルが検証対象です。評価が高かったTHNSNS***GBSPシリーズ(砂芝)の後継製品であり、2013年4月の発売開始以来、大人気で品切れ状態が続いていましたが、6月に入ってようやく短納期で入手できるようになりました。amazon等の通販サイトでは常に売り上げランキング上位に入る人気商品になっています。
東芝SSD HG5dシリーズは、俗に言う「マベ芝」のSSD製品で、Marvell製コントローラーをベースにした東芝カスタムコントローラー「TC58NC5HA9GST」と東芝製「19nm MLC NAND Flash」を搭載しています。DRAMキャッシュを搭載していないにも関わらず、Marvellコントローラと東芝NANDの実力によって98,000IOPS以上という高速なランダムアクセス性能を謳う製品ですが、read/writeが混在する高負荷I/Oが30分以上継続した時にも実力を発揮できるでしょうか。
PLEXTOR PX-256M5P 256GB 高負荷ベンチマーク結果&チューニングTips

高いI/O負荷を連続して掛けた時に各社のSSDがどのような性能特性を示すか、ベンチマークツールを利用して計測していきます。
今回はPLEXTOR M5Pro(前期型・BGAタイプ)の256GBモデルが検証対象です。プレクスター製SSDの中でフラグシップモデルに位置付けられる最上位の製品です。
PLEXTOR M5Proシリーズは、“サーバグレード”と位置付けられるMarvell 88SS9187コントローラーと512MBのキャッシュメモリの組み合わせによって、10万IOPSという高速なランダムアクセス性能を謳う意欲的なSSD製品ですが、read/writeが混在する高負荷I/Oが30分以上継続した時にも実力を発揮できるでしょうか。
Samsung SSD 840 PRO 256GB 高負荷ベンチマーク結果&チューニングTips

高いI/O負荷を連続して掛けた時に各社のSSDがどのような性能特性を示すか、ベンチマークツールを利用して計測していきます。
今回はSamsung SSD 840 PRO Seriesの256GBモデルが検証対象です。サムソン製SSDの中でフラグシップモデルに位置付けられる最上位の製品です。
Samsung SSD 840 PRO Seriesは、自社製の3-Core MDXコントローラーと512MBのキャッシュメモリの組み合わせによって、10万IOPSという高速なランダムアクセス性能を謳う意欲的なSSD製品ですが、read/writeが混在する高負荷I/Oが30分以上継続した時にも実力を発揮できるでしょうか。
Intel SSD 520 Series 240GB 高負荷ベンチマーク結果&チューニングTips

高いI/O負荷を連続して掛けた時に各社のSSDがどのような性能特性を示すか、ベンチマークツールを利用して計測していきます。
今回はIntel SSD 520 Seriesの240GBモデルが検証対象です。コンシューマー向けに販売されるインテル製SSDの中ではフラグシップモデルに位置付けられる上位の製品です。
Intel SSD 520 SeriesはSandForceコントローラー「SF-2281VB1-SDC」を搭載しており、圧縮アルゴリズムを活かした高速なスループット性能を誇ることから「直線番長」「0fill番長」等とも揶揄される製品ですが、read/writeが混在する高負荷I/Oが30分以上継続した時にも実力を発揮できるでしょうか。
SSD I/Oブロックサイズの調整によるチューニング効果検証 (東芝THNSNS240GBSP編)

SSDに対するI/Oのブロックサイズ(アロケーションユニットサイズ)を調整することによって、I/O性能をどの程度向上させることができるでしょうか。今回は東芝製SSD「THNSNS240GBSP」(IODATA SSDN-3T240B、CFD CSSD-S6T240NTS2Q)を使って、ブロックサイズの調整によるチューニング効果を検証します。
THNSNS***GBSPシリーズは、俗に言う「砂芝」のSSD製品で、SandForce製コントローラー「SF-2281/2282」をベースにした東芝カスタムコントローラー「TC58NC5HJ8GSB-01」と東芝製「24nm MLC NAND Flash」を搭載しています。ページサイズは公表されていません。
(参考 : TOSHIBA – The TOSHIBA THNSNS solid state drives )
SSD I/Oブロックサイズの調整によるチューニング効果検証 (DC S3700編)

SSDに対するI/Oのブロックサイズ(アロケーションユニットサイズ)を調整することによって、I/O性能をどの程度向上させることができるでしょうか。エンタープライズ利用に対応する「Intel SSD DC S3700 Series」の200GBモデルを使って、ブロックサイズの調整によるチューニング効果を検証しました。
チューニングによってI/O性能の向上を期待できる要因としては、データを読み書きする都度データの記録位置にヘッドを動かしプラッタを回転させるHDDに対して、SSDはデータ読み書き時の挙動が根本的に異なることです。HDDは必要な複数のデータが1つのブロック内に保存されていれば、ヘッドを動かしプラッタを回転させる時間、すなわちシークタイムが減少します。これに対して、SSDには可動部が無くNANDメモリーを記録域として電気的に情報を読み書きしますので、必要な複数のデータが離れたブロックに保存されていても性能影響を受けないと考えられます。
Linuxカーネルパラメータ一覧・標準設定 (CentOS 6)
Windows7の遅いXPモードを劇的に高速化する方法
Fusion-io ioDrive の“非公式”標準価格/販売価格表
Linuxファイルシステムベンチマーク第2回 ext3,ext4,JFS,ReiserFS,XFS,NILFS2

ext3ファイルシステムは、機能面・信頼性・性能面で非常にバランスの取れたファイルシステムであり、多数のディストリビューションで「標準のファイルシステム」として採用・サポートされてきました。現時点(2009年時点)では事実上、「Linux標準ファイルシステム」の地位を築いていると言っても過言ではありません。
しかしながら、Linux標準ファイルシステムのext3だけではなく、他ファイルシステムへの対応やサポートを売りにするディストリビューションも数多く登場しています。また、ext4やbtrfs等、次のLinux標準ファイルシステムと目されるファイルシステムも、現在、非常に活発に開発が進められています。このような状況の中、ext3から他のファイルシステムに乗り換える価値、他のファイルシステムを採用する価値はどの程度あるのでしょうか。
Linuxファイルシステムベンチマークの第2回は、カーネル2.6.30で有力な選択肢となる6つのファイルシステム、ext3、ext4、JFS、ReiserFS、XFS、NILFS2を対象に「bonnie++」を用いた性能ベンチマークを行い、複数のファイルシステムを性能面から比較してみました。
Linuxファイルシステムベンチマーク第1回 ext2,ext3,JFS,ReiserFS,XFS,NTFS

ext3ファイルシステムは、機能面・信頼性・性能面で非常にバランスの取れたファイルシステムであり、多数のディストリビューションで「標準のファイルシステム」として採用・サポートされてきました。現時点(2009年時点)では事実上、「Linux標準ファイルシステム」の地位を築いていると言っても過言ではありません。
しかしながら、Linux標準ファイルシステムのext3だけではなく、他ファイルシステムへの対応やサポートを売りにするディストリビューションも数多く登場しています。また、ext4やbtrfs等、次のLinux標準ファイルシステムと目されるファイルシステムも、現在、非常に活発に開発が進められています。
このような状況の中、ext3から他のファイルシステムに乗り換える価値、他のファイルシステムを採用する価値はどの程度あるのでしょうか。ファイルシステムのベンチマークツール「bonnie++」を用いて性能ベンチマークを行い、複数のファイルシステムを性能面から比較してみました。
チップセットモデル図から考えるハードディスク性能比較

たとえ多くのハードディスクを連ねてRAID構成を組みディスクストレージ構成のIO性能向上を計ったとしても、接続するインターフェースによって性能限界が存在します。ここでは、IAサーバのチップセットモデル図から、IDE、SCSI、NAS(NFS)、SAN(FC)等、接続インターフェースの違いによるHDDの性能比較について考えます。
例えば、NASを100BASE-TXのネットワークで利用した場合、IDEで接続するHDDよりIO性能が低いということは、NAS環境の導入・利用経験のある方なら容易に想像できると思います。Windowsサーバによるファイル共有環境を想像して頂いても感覚がつかめるでしょう。あくまで通信のオーバーヘッド等を考慮しない理論上の数値になりますが、現在最も普及しているIDE(Ultra ATA/100規格)の最大データ転送速度が「100MB/sec」であるのに対して、100BASE-TXの最大転送速度は「12.5MB/sec」です。